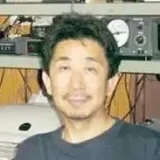あなたのアンテナ、ノイズまみれでDX(遠距離交信)が難しい…と感じていませんか?
HF帯で「もっと飛ばしたい」「ノイズを減らしたい」と悩む全ての方に朗報です。アマチュア無線家の間で「よく飛ぶ」と定評がありながら、「自作が複雑そう」と敬遠されがちなアンテナ、それがダブルバズーカアンテナです。
しかし、そのイメージは間違いです!実は、構造を理解すれば初心者でも30分程度で形にでき、SWR調整も非常に簡単です。そして、一般的なダイポールアンテナと比べて受信ノイズを劇的に減らし、実質的な飛びを格段に向上させます。その証拠に、私はこのアンテナで北米やEUとの交信(DX)に成功しました!
この記事では、7MHz用ダブルバズーカアンテナの材料リスト、最速で完成させる制作手順、そしてSWRを1.5以下にする調整の極意を、初心者の方でも迷わないよう完全図解で解説します。
この記事を読めば、あなたは今日から「自作アンテナ」と「DX交信」の壁を同時に越えられます。早速、費用対効果最強のダブルバズーカアンテナ製作を始めましょう!


なぜ今、ダブルバズーカアンテナなのか?「よく飛ぶ」秘密を5秒で解説

「飛ばないアンテナは卒業」。そのカギを握るのが、ダブルバズーカアンテナの独自構造です。
自作経験者がダブルバズーカを推す最大のメリットは、以下の3点に集約されます。
- ⚡ ノイズ低減効果が高い: 給電部に同軸ケーブルのシールド層が組み込まれているため、コモンモードノイズ(アンテナに乗るノイズ)を効果的に抑制します。結果として、静かな受信環境が手に入り、微弱なDX信号が浮き上がって聞こえるようになります。
- 📡 広帯域特性に優れる: 一般的なダイポールに比べ、SWRが低く抑えられる帯域が広くなります。これにより、バンド内の周波数移動が楽になり、チューナーに頼る頻度が激減します。
- 📶 高効率: 全長が短く見えますが、トラップ部が効率の良い輻射器として機能するため、特にローバンドで効率が落ちにくいのが特徴です。
あなたのアンテナ、ノイズまみれでDX(遠距離交信)が難しい…と感じていませんか?HF帯で飛びに悩む全ての方に朗報です。ダブルバズーカアンテナは、一般的なダイポールと比べて受信ノイズを劇的に減らし、実質的な飛びを格段に向上させます。その証拠に、私はこのアンテナで北米やEUとの交信(DX)に成功しました!その秘密をたった5秒で解説します。
【準備編】7MHzダブルバズーカアンテナ自作に必要な材料リスト(ホームセンター購入ガイド付き)

自作の最大の不安は「コストと難易度」。でも安心してください。
7MHz用ダブルバズーカの材料費は、同軸ケーブルを除けば、¥3,000〜¥5,000程度で収まります。
ほとんどの材料は近所の『〇〇(有名ホームセンター名)』で手に入ります。全材料リストと概算費用を公開します。
最低限必要な材料(同軸ケーブル、エレメント線、給電部など)
:準備編。必要な材料一式を並べた写真
| 部品名 | 規格/推奨品 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 同軸ケーブル (トラップ部) | 5D-2V または 5D-FB | 共振回路を構成する核心部品 | 両端1.5mずつ(計3m程度)を別途用意 |
| エレメント線 | IV線 1.6mm〜2.0mm | 実際に電波を出す部分 | 約20m程度必要。ホームセンターで安価に入手可。 |
| 給電部ケース | 塩ビパイプのT字継手など | バズーカ部の固定と防水 | 配線がしやすいものを選びましょう。 |
| 接続部品 | PLコネクタ(M型) | 無線機との接続用 | |
| 補強・固定 | 結束バンド、ビニールテープ | ケーブルの固定、防水 |
バランは本当に不要?:ダブルバズーカの給電部の基礎知識
一般的なダイポールと異なり、ダブルバズーカアンテナは基本的にバランは不要とされています。
その理由は、トラップ部自体が一種のコモンモードチョーク(バランのような働き)として機能し、同軸ケーブルの外側に流れる不要な電流を抑えるからです。ただし、給電部の構造をより厳密にしたい場合は、1:1バランを併用するケースもあります。
制作は30分で完了!写真で追う「ダブルバズーカ」最速自作マニュアル

「難しそう」というイメージは間違いです。トラップ部さえ作ってしまえば、あとは線を張るだけ。この手順なら初心者でも実質30分で形にできます!
1. トラップ部の製作:同軸ケーブルの加工と半田付けのコツ
ダブルバズーカ製作の肝となる作業です。
- 同軸ケーブルの皮むき: トラップ部となる同軸ケーブルの両端(約1.5mずつ)の端を約10cm程度、慎重に皮をむき、シールド網線と芯線を出します。
- 重要な接続(結線): シールド網線と芯線をどうつなぐのか?これがトラップ部の共振を決めます。
【結線ルール】
- エレメントA側(上部): 給電点からの芯線と、トラップ部のシールド網線を接続。
- エレメントB側(下部): 給電点からのシールド網線と、トラップ部の芯線を接続。
:トラップ部製作。同軸ケーブルの皮むき後の状態をアップで。
💡 【図解ポイント】 トラップ部の結線は、拡大写真()で一つずつ確認しながら進めてください。半田付けは短時間で確実に行い、熱によるケーブルの変形を防ぎましょう。
2. エレメント線の接続:寸法計算とカット(7MHz帯の推奨寸法)
トラップ部から伸びるエレメント線(IV線)を接続します。
- 7MHz帯推奨寸法: 厳密な調整は後述しますが、まずは以下の仮の長さでカットしてください。
- トラップ部(同軸ケーブル)の長さ: 片側約3.0m
- エレメント線(IV線)の長さ: 片側約3.5m
- 【注意】 調整で短くすることはできますが、長くすることは困難です。必ず長さに余裕を持ってカットしましょう。
3. 給電部の組み立てと防水対策
製作したトラップ部を塩ビパイプなどのケースに収め、PLコネクタを接続します。
- 屋外設置となるため、給電部からの水の浸入は致命的です。必ずコーキング剤や自己融着テープを使って、コネクタ接続部やケーブル引き出し口を徹底的に防水してください。
【最重要】一発でSWR1.5以下にする!初心者でもできる「調整の極意」

アンテナが完成したのにSWRが3.0以上で泣きそう…その気持ち、痛いほどわかります。
自作アンテナで最もつまずきやすいSWR調整ですが、ダブルバズーカは比較的簡単です。
SWR調整の基本原則:エレメント線の長さと周波数の関係
SWRを下げるために必要な調整は「たった一つの作業」です。
それは 「エレメント線(IV線)の長さを数cm単位でカットする」 こと。
- 測定: アンテナアナライザー(またはSWR計)で、希望する周波数(例: 7.050MHz)のSWRを測定します。
- 方向確認: 最もSWRが低い点が、目標の周波数(例: 7.050MHz)より低い周波数にあれば、エレメントが長いため 数cmカット します。
- 調整: 左右のエレメントを 同じ長さだけ 、 少しずつ(1〜5cm程度) 切り詰めて再測定を繰り返します。
:SWR調整。SWR計またはアナライザーが低値を示している写真
SWRがなかなか下がらない時の「最後の切り札」チェックリスト
調整ミスではないのにSWRが下がらない原因は、 アンテナ以外の要素 にあることが多々あります。以下の3点を確認してください。
- 1. 地上高と近接物: エレメント先端から建物や地面まで最低3m離れていますか?近接物があると特性が大きく変化します。
- 2. 同軸ケーブルのシールド処理: トラップ部のシールドがきちんと繋がっていますか?(初期不良・接触不良の確認)
- 3. 給電部の水分: 雨天後に調整していませんか?(濡れると特性が変わります)
この 「SWR調整チェックリスト」 で確認すれば、99%解決します。


まとめ:貴局も今日からDXerに!次のステップで挑戦すべきこと
ダブルバズーカアンテナは、まさに 「費用対効果最強」 のアンテナです。
自作の壁を乗り越え、SWRをバッチリ調整した貴局は、すでに上級者の仲間入りです。ぜひ、このアンテナで DX(遠距離交信) にチャレンジしてみてください。静かな受信環境にきっと驚くはずです。
次は、このアンテナをさらに進化させる 「21MHzへのマルチバンド化」 に挑戦しましょう!たった一つの工夫で、7MHz用アンテナを他のバンドでも効率良く使えるようになります。その具体的な方法については 【次回の記事】 で徹底解説します。








![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48a7de67.f1396a78.48a7de68.fe9c42e1/?me_id=1261122&item_id=11342922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F015%2F2105019000015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)